「ニュー・アース―意識が変わる 世界が変わる―」(サンマーク出版)
エックハルト・トール(著),吉田 利子(翻訳)
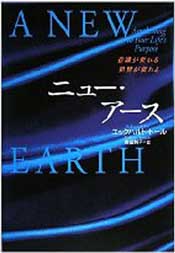
第1章 私たちはいますぐ進化しなければならない
花、開く
一億一千四百万年前のある朝、夜が明けてまもないころ、昇る朝日を受けて一輪の花がぽっかりと開く。
地球という星の最初の花だ。
すでに何百万年か前から地球には植物が茂っていたが、この最初の開花は植物という生命体の画期的な進化と変容を告げる出来事だった。
しかし最初の花はたぶん長くはもたず、その後も依然として開花はめったにない特殊な現象に留まっていたことだろう。
花々が広く咲き誇るための条件はまだ整ってはいなかったはずだから。
だがある日、植物の進化は決定的な閾値(いきち)に達し、地球のありとあらゆるところに――それを目撃して認識できる存在があったとすれば――色彩と香りが爆発的に広がり始める。
それからだいぶたって、私たちが花と呼ぶ香り高く繊細な存在は、他の種の意識の進化に欠かすことのできない役割を担いだす。
人類はますます花にひきつけられ、魅せられる。
人類の意識が進化するなかで、実用的な目的をもたない、つまり生存と結びつかないのに高く評価された最初の対象はきっと花だったに違いない。
花々は無数の芸術家、詩人、神秘主義者にインスピレーションを与えてきた。
イエスは、花について思え、そして花から生き方を学べ、と語った。
ブッダはあるとき、弟子たちを前に一本の花を掲げ、「黙して語らなかった」という。
しばらくして弟子たちの一人、摩訶迦葉(まかかしょう、マハーカッサパ)という僧が微笑んだ(拈華微笑、ねんげみしょう)。
摩訶迦葉だけがブッダの沈黙の教えの意味を理解したのだ。
言い伝えによれば、この微笑(悟り)はその後二十八代の師に伝えられ、やがて禅の始まりになった。
花に美を見出すことを通じて、人類はほんのつかの間であれ、自分の最も内なる存在の核心にある美や本質に目覚めるのではないか。
美というものの最初の認識は、人類の意識の進化にとって最も重要な出来事の一つだった。
その認識と本来的に結びついているのが喜びと愛という感情である。
それとははっきりと気づかないうちに、花々は私たちにとって、自らのなかの最も高貴で聖らかな、究極的には形になり得ないものを表現するものになった。
生まれ出るもとの植物よりももっとはかなくて美しく繊細な花々は別の領域から来たメッセンジャー、物理的な形の世界と形のない世界をつなぐ橋のようなものだ。
花々には人々を喜ばせる繊細な良い匂いがあるだけではなく、霊性の領域の香りをも運んでくる。
「悟り」という言葉をふつうに言われるよりも広い意味で使うなら、私たちは花々に植物の悟りを見ることができる。
どの領域のどんな生命体も――鉱物、植物、動物、あるいは人間も――「悟り」を体験すると言える。
だがそれは進化の延長ではないからこそ、きわめて稀な出来事だ。
発展のなかの断絶、まったく別のレベルの存在への飛躍、そして何より大事なことに物質性の減少を意味するのである。
あらゆる形のなかでも最も密な岩、それよりもさらに重くて固いものがあるだろうか?
しかしその岩のなかには、分子構造に変化が起こって、光を透過させる結晶と化すものがある。
また炭素のなかには想像を絶する熱と圧力を経てダイヤモンドになるものがあるし、その他の貴石と化す重い鉱物もある。
あらゆる生物のなかでも最も地に縛りつけられている爬虫類のほとんどは、何百万年も変わらず地を這い回っていた。
だがそのなかには羽や翼が生えて鳥になり、長いあいだ彼らをつなぎとめてきた重力に挑んで羽ばたいたものがあった。
彼らは這い回ったり歩き回ったりすることが巧みになったのではなく、這い回り歩き回ることを完全に超えた。
有史以前から花々や結晶、貴石それに小鳥は、人類の魂にとって特別の意味をもっていた。
もちろんいずれも、他のあらゆる生命体と同じくすべての源であるひとつの「生命」、ひとつの「意識」が一時的に形となって現れたものだ。
これらがなぜ特別の意味をもち、なぜ人類がこれほど魅了され共感を覚えるのか、それはその美という特質に帰することができるだろう。
人間がある程度「いまに在る」という本質的な生き方ができるようになり、外界への静かで鋭敏な意識が芽生えると、生命の聖なる本質、つまりすべての生物、あらゆる生命体に存在する意識あるいは魂を感じ取り、それが自分自身の本質でもあると気づいて愛するようになる。
だがそれまでは、たいていは外形的な姿ばかりを見て、内なる本質になかなか気づかない。
自分自身の本質がわからず、肉体的、心理的な形が自分であると信じ込む。
しかし先に述べた「いまに在る」生き方にろくに、あるいはまったく達していない者でも、花や結晶や貴石や小鳥に物理的な存在以上のものを感じ取って、それがひかれる理由だと自覚しないままに、同じ仲間だと親近感を覚えることがある。
これらは美しいがゆえにへ他の生命体ほどには内なる魂が形に曇らされていない。
ただ生まれ落ちたばかりの生命体――赤ちゃん、子犬、子猫、子羊など――はちょっと違う。
生まれたばかりの生き物は脆くて華奢(きゃしゃ)で、まだ物質性がさほど確立していない。
この世のものならぬ無垢(むく)で甘やかな美が輝き出ている。
だからどちらかというと鈍感な人でさえ、赤ん坊を見ればなんだか嬉しくなる。
そこで花や結晶や小鳥の名称を意識せずに虚心に見つめ、思いを寄せると、形のないものへの窓口が見えてくる。
ほんのわずかな隙間ながら、魂(スピリット)の領域に通じる内なる道が開けるのだ。
だからこの三つの「悟りに達した」生命体は、古代から人類の意識の進化のなかで非常に重要な役割を演じてきた。
たとえば、なぜ蓮華の玉が仏教の中心的象徴になったのか、なぜキリスト教では白い小鳩が聖霊を表すのか。
これらは人類に運命づけられた地球的意識のさらに奥深い変化への土台を準備してきたのである。
その変化こそ、いま私たちが目の当たりにしようとしているスピリチュアルな目覚めなのだ。
変化をもたらすためのツール
人類の意識の変容への準備、どれほど美しい花もこれに比べれば色あせてしまうほど根源的で奥深い内なる開花への準備は整っているのだろうか?
人間は、条件づけられた鈍くて重い心の構造から脱却して、いわば結晶や貴石のように、意識の光を透過させることができるのか?
物質主義と物質性の重力を拒否し、エゴを支え一人一人を個としての存在に閉じ込めておく形への同一化から抜け出して、飛び立つことができるのか?
このような変容は可能だ。
それが人類の偉大な智恵が教える中心的なメッセージである。
そのメッセージを伝えた人々は――プツダ、イエス、その他名前が知られていない人々も――すべてへ早い時代に開いた人類の花だ。
彼らは先駆者であり稀少で貴重な存在だった。
花々が広く咲き誇る時期はまだ来ていないし、彼らのメッセージの多くは誤解され、しばしば大きく歪められてきた。
そしてごく少数を除いて、人類の行動が変わらなかったことも確かである。
ではこれら初期の指導者たちの時代に比べて、いまのほうが人々の準備は整っているのだろうか?
どうすればそれがわかるのか?
この内的な変化をもたらす、あるいは加速することができるとしたら、何をすればいいのか?
古いエゴイスティックな意識の特徴はどんなことで、どんなしるしを見れば新たに芽生えようとする意識がわかるのか?
本書ではこうした核心的な問題を取り上げる。
だがもっと重要なのは、新しい意識から生まれた本書自体が、変化をもたらすためのツールだということだ。
ここに示される考え方や概念も重要だろうが、しかしそれは二次的なことである。
目覚めへの道を指し示す道標にすぎない。
本書をお読みになるうちに、あなたのなかで変化が起こるだろう。
本書のいちばんの目的は、読者の頭に新しい情報や信念を付け加えることでも、何かを説得することでもなく、意識を変化させること、つまり目覚めさせることだ。
その意味では本書は「おもしろく」はないかもしれない。
おもしろがるとは、対象から距離を置いて、考え方や概念を頭のなかでもてあそび、同意したり反論したりすることだからである。
本書の当事者はあなた自身だ。
あなたの意識の状態が変わらないなら、本書の意味はない。
だが目覚めることができるのは、準備が整った者だけだ。
まだ全員というわけではないが、準備ができている人は多いし、一人が目覚めるたびに集団的な意識のうねりは大きくなり、その他の人々の目覚めが容易になる。
目覚めるということの意味がわからない方は、本書を読み続けていただきたい。
目覚めることによってのみ、目覚めるとは何なのかが、ほんとうに理解できる。
わずかに垣間見るだけでも目覚めのプロセスが始まるには充分だし、いったん始まったプロセスは後戻りしない。
本書を読むことでそのプロセスを垣間見る人もいるだろうし、自分では気づいていなくてもすでにプロセスが始まっている人も多いだろう。
その人たちは本書を読むことでプロセスに気づくはずだ。
またある人々にとっては喪失や苦しみが、また別の人々にとってはスピリチュアルな指導者や数えに触れ、人生を変えるような本(そのなかには私の著書『さとりをひらくと人生はシンプルで楽になる』[徳間書店刊]も含めたい)を読むことが、あるいはこれらの組み合わせが、目覚めのきっかけになるかもしれない。
あなたのなかで目覚めのプロセスがすでに始まっているとしたら、本書によってそのプロセスは加速され、充実したものになるだろう。
目覚めに不可欠なのは目覚めていない自分を自覚すること、エゴイスティックに考え、話し、行動する自分と、そういう目覚めていない状態を持続させている、人類に刷り込まれた思考プロセスを認識することである。
だから本書ではまずエゴの主な側面に目を向け、それが個人や集団でどう働いているかを考える。
これには二つの重要な理由がある。
第一の理由は、エゴが働く基本的な仕組みを知らなければエゴを認識できず、そのためにだまされっぱなしで何度でもエゴを否認することになるからだ。
つまりあなたは支配され、操られ続ける。
第二の理由は、認識そのものが目覚めの一つの方法だからである。
自分のなかの無意識を認識するとき、認識を可能にするのは意識の覚醒、つまり目覚めである。
エゴと闘っても勝ち目はない。
闇と闘えないのと同じである。
必要なのは意識という光のみである。
そして、その光はあなたなのだ。
人間に固有の機能不全
古い宗教やスピリチュアルな伝統をよくよく見れば、表面的な違いはどうあれ、その多くに共通する二つの中心的な洞察があることに気づくだろう。
その洞察を表す言葉は異なるが、どれも基本的な真実の二つの面を指し示している。
一つはほとんどの人間の「ふつうの」精神状態には機能不全、もっと言えば狂気と呼べるような強力な要素が含まれていることだ。
とくに手厳しいのはヒンズー教の中核となる教えの一つで、この機能不全を集団的な精神病と見なし、マーヤー、妄想のベールと呼ぶ。
インドの偉大な賢者の一人ラマナ・マハリシは、「心とは妄想である」と言い切っている。
仏教では別の言葉を使う。ブッダによれば、ふつうの状態の人間の心はドゥッカ、苦を生み出す。
苦、不満、惨めさである。
ブッダはそれが人間の置かれた状況の特徴だと見た。
どこにいても、何をしていても、あなたはドゥッカにぶつかるし、ドゥッカは遅かれ早かれあらゆる状況に現れる、とブッダは言う。
キリスト教の教えでは、人類という集団のふつうの状態が「原罪」である。
罪という言葉は大いに誤解され、間違って解釈されてきた。
新約聖書が書かれた古代ギリシャ語を文字通りに訳せば、罪とは射手の矢が標的からそれるように的を外れることだ。
したがって、罪とは的外れな人間の生き方を意味する。
先を見ないで不器用に生きて苦しみ、人をも苦しませるのが罪なのだ。
文化的な覆いや誤解をはぎ取ってみると、ここでも人類の状況に固有の機能不全を指していることがわかる。
人類がめざましい発展をしてきたことは否定できない。
人間は音楽や文学、絵画、建築、彫刻などの数々の傑作を生み出してきた。
さらに最近では科学技術の発達によって暮らし方がまったく変わり、ほんの二百年前なら奇跡としか思えなかったことも可能になった。
これは疑いようがない。
人類は大変に知的なのだ。
だがその知性は狂気を帯びている。
科学技術は人類の精神につきまとう機能不全が地球に、他の生命体に、そして人類自身に及ぼす破壊的影響をさらに拡大してきた。
だからその機能不全、集団的狂気は二十世紀の歴史で最もあらわになった。
しかもこの機能不全は現実に強化、加速されている。
第一次世界大戦は一九一四年に勃発した。
恐怖と貪欲さと権力欲が引き起こす破壊的で残虐な戦いは、宗教やイデオロギーに基づく奴隷制や拷問、暴力の蔓延と同様に、人類の歴史を通じてありふれた出来事だった。
人類にとっては自然災害よりもお互いが引き起こす災厄の苦しみのほうがはるかに大きかったのである。
しかし一九一四年を迎えるまでに、きわめて知的な人類はエンジンだけでなく爆弾、機関銃、潜水艦、火炎放射器、毒ガスを発明していた。
狂気に仕える知性!
戦況が膠着したフランスとベルギーの国境付近では、泥土を数マイル前進するために数百万の男たちが塹壕で死んでいった。
一九一八年に戦いが終わると、生き残った者たちは信じがたい思いと恐怖で破壊の跡を見つめた。
一千万人が殺され、さらに多くが負傷し、身体の一部を奪われた人々もいる。
人類の狂気がこれほどの破壊をもたらしたことも、それがこれほど白日の下にさらされたこともかつてなかった。
しかもこれがほんの始まりだとは、誰も知る由もなかったのである。
二十世紀の終わりまでに、同じ人類の手で暴力的な死を遂げた人々の数は一億人を上回った。
国家間の戦争だけでなく、スターリン統治下のソ連で「階級の敵、スパイ、裏切り者」として殺された二千万人や、ナチス・ドイツによる筆舌に尽くしがたい恐怖のホロコーストの犠牲者たちのように、大量殺戮や集団虐殺によって死んでいった人々もいる。
さらにスペイン内戦や、人口の四分の一が殺害されたクメール・ルージュ体制のカンボジアなど、数え切れない内戦の犠牲者もいた。
このような狂気が衰えるどころか二十一世紀のいまも続いていることは、日々のテレビニュースを見るだけですぐにわかる。
人類の集団的な機能不全のもう一つの側面は、他の生命体と地球そのものに人間たちが振るっている暴力だ。
酸素を生み出す森林や植物、動物の破壊と殺害。
工場式農場における動物虐待。
河川や海、大気の汚染。
人間たちは欲に駆られ、自分と全体のつながりを理解せず、ほうっておけば自滅につながるだけの行動をいまも続けている。
人間の存在の核心にある集団的狂気が引き起こす出来事は、人類史の大きな部分を占めている。
人類の歴史は、おおまかに言えば狂気の歴史なのである。
これが個人の病歴だとしたら、こんな診断がつくに違いない。
慢性的偏執性妄想、「敵」と思い込んだ――自らの無意識の投影である――相手への病的殺人癖と暴力と残虐性。
たまに短期間正気を取り戻すだけの犯罪狂。
恐怖、食欲さ、権力欲は、国家や民族、宗教、イデオロギー間の戦争と暴力の心理的動機となっているだけでなく、個人の人間関係の絶え間ない葛藤の原因でもある。
これが他人だけでなく自分についての認識を歪める。
そのためにあらゆる状況を間違って解釈し、恐怖を解消しよう、「もっと多く」を求める自分の必要性を満たそうと、間違った行動に出る。
この「もっと多く」という欲求は、決して満たされることのない底なしの穴だ。
しかしこの恐怖と食欲さと権力欲はここで言う機能不全そのものではなく、それぞれの人間の心のなかに深く根を下ろした集団的妄想という機能不全の結果である。
多くのスピリチュアルな教えは、恐怖と欲望を捨てなさいと言う。
だがこの試みはたいていはうまくいかない。
機能不全の根源に取り組んでいないからだ。
恐怖と食欲さと権力欲は究極の原因ではない。
もっと良い人間になろうと努力するのは確かに立派でほめられるべきことのようだが、当人の意識に変化が起こらない限り、結局は成功しない。
良い人間になろうとするのもまた同じ機能不全の一部で、微妙でわかりにくい形ながら、やはりエゴイスティックな高揚感、自意識や自己イメージの強化を求める欲であることに変わりはない。
良い人間、それは、なろうとしてなれるものではない。
すでに自分のなかにある善を発見し、その善を引き出すことでしか、良い人間にはなれない。
だがその善を引き出すためには、意識に根本的な変化が起こる必要がある。
もともとは高潔な理想から始まった共産主義の歴史は、人々がまず自分の意識状態という内なる現実を変化させようとせずに、ただ外部的現実を変えようと――新しい地を創造しようと――試みるときに何が起こるかを明白に示している。
共産主義者は、すべての人間がもっている機能不全の青写真を考慮せずに行動計画を立てた。
その機能不全とはエゴである。
新しい意識
古い宗教やスピリチュアルな伝統のほとんどに共通する洞察がある。
われわれの「ふつうの」精神状態には基本的な欠陥があるということだ。
しかし人間存在の本質に関するこの洞察――これを悪いニュースと呼ぼうか――から、第二の洞察が生まれる。
人間の意識の根源的変化の可能性という良いニュースである。
ヒンズーの(仏教にも共通する)教えでは、この変化を「悟り」と呼ぶ。
イエスの教えでは「救済」、仏教では「苦滅諦」と言う。
「解放」や「目覚め」という言葉が使われることもある。
人類にとって最大の成果は芸術作品でも科学でも技術でもなく、自らの機能不全、狂気の認識だ。
遠い昔にすでにこの認識に到達していた人々がいた。
たぶんこの機能不全を最初に絶対的な明断さで見抜いたのは、二千六百年前のインドにいたゴータマ・シッダルタである。
ほぼ同時に中国にも目覚めた人類の教師が現れた。
その名を老子という。
老子は最も深い霊的な書物の一つである『道徳経』という形で、その教えを遺した。
もちろん自らの狂気を認識することが正気の台頭であり、治癒と変容の始まりである。
すでに地球上には意識の新たな次元が現れ、最初の花々が少しずつ開き出している。
これまでごく少数ではあるが、同時代人に語りかけた人たちがいた。
彼らは罪について、苦しみについて、妄想について語った。
「自分の生き方を見てごらん。自分が何をしているか、どんな苦しみを生み出しているかを見てごらん」と。
それから彼らは「『ふつうの』人間存在という集団的な悪夢から目覚めることができるのだよ」と指摘した。
彼らは道を示した。
この人たちは人類の目覚めに必要不可欠だったが、世界の側の準備はまだできていなかった。
だからたいていは同時代人に、そして後世の人々にも誤解された。
彼らの教えはシンプルで力強かったが、歪められ、間違って解釈され、場合によっては弟子たちに誤って記録された。
何世紀かが過ぎるあいだ、本来の教えとは何の関係もない、それどころか基本的な誤解を反映する多くのことが付け加えられていった。
これら人類の教師たちのなかには馬鹿にされ、罵(ののし)られ、殺された者さえいた。
またある者は神として崇められた。
人類の精神の機能不全を克服する道、集団的狂気から脱出する方法を示した教えは歪められ、それ自身が狂気の一部となった。
こうして、宗教は人々をまとめるよりもむしろ分断する力となってきた。
生きとし生けるものはひとつであるという認識を通じて暴力や憎悪に終止符を打たせるのではなく、もっと激しい暴力や憎悪を引き起こし、人間同士を、異なる宗教を、さらには同じ宗教の内部までを分裂させたのである。
宗教はイデオロギーになり、人々が自分を同一化させ、間違った自我意識を強化しようと試みる信念体系になった。
人々はこの信念をよりどころに自分が「正しく」て相手が「間違っている」と断じ、敵を、「他者」「異端」「間違った思想の持ち主」と呼んだ。
それによって自分のアイデンティティを確立しようとし、対立者の殺害すらもたびたび正当化した。
人間は自分の姿を象(かたど)って「神」をつくった。
永遠、無限、名づけようのない真実は、「私の神」「私たちの神」として信じ崇拝すべき偶像に堕落した。
だが――宗教の名ではびこってきたこのような狂気の行動にもかかわらず――それでもなお――核心部分では各宗教が指し示した真実が依然として輝いている。
どれほどかそけき光であろうとも、何層もの歪曲や誤解を貫いていまも輝き続けている。
ただし人は自らのなかにその真実の片鱗を垣間見ない限り、その光を認識できない。
歴史を通じて少数ながらつねに意識の変容を経験し、すべての宗教が指し示すものを自らの内に発見した人々がいた。
彼らはこの概念化できない真実を表現するために、それぞれの宗教の概念的枠組みを利用した。
主要な宗教のいずれにも、このような人々が起こした「宗派」や運動があり、そこでは本来の数えの光が再発見されているだけでなく場合によってはさらに強く輝き出した。
キリスト教の初期及び中期のグノーシス主義や神秘主義、イスラム教のスーフィズム、ユダヤ教のハシディズムやカバラ、ヒンズー教のアドヴァイタ・ヴェーダンタ、仏教の禅や不二一元論(ゾクチェン)などである。
これらの宗派のほとんどは因習を打破し、偶像を破壊した。
宗教につきまとう何層もの概念化と信念構造の殻を打ち破りそれゆえにほとんどが既成宗教のなかで疑惑の目を向けられ、多くは敵意にさらされた。
主流の宗教と違って、これらの宗派の教えは認識と内なる変化を強調した。
主要な宗教はこのような秘教的な教えや運動を通じて本来の教えがもつ変容力を回復したのだが、ほとんどの場合、そこに近づけるのはごく少数の人々だけだった。
多数派の深い集団的無意識にそれなりの影響を及ぼせるほど、その人々の数が増えることはなかった。
また時の移り変わりとともに、これらの秘教的宗派そのものが硬直し、形骸化し、概念化して、効力を失っていった。
スピリチユアリティと宗教
新しい意識の高まりのなかで、既成宗教はどのような役割を担うだろう?
多くの人々はすでにスピリチュアリティと宗教の違いに気づいている。
信念体系――自分が絶対的真実だとみなす一連の考え方――は、どのようなものであれ、持ち主をスピリチュアルにはしない。
それどころかその考え方(信念)と自分を同一化すればするほど、自分のなかのスピリチュアルな面から切り離されていく。
「信仰心篤い」人たちの多くはこのレベルに留まっている。
思考を真実と同一視し、その思考に自分を完全に同一化しているので、自分だけが真実を知っていると主張するが、実は無意識のうちに自分のアイデンティティを守ろうとしているだけだ。
この人たちは思考の限界に気づかない。
自分の行動と信念に完全に同意しない人間は間違っていると決めつけ、そう遠くない過去には、相手を殺害することも正当化されると考えていた。
いまでもそう思っている人たちがいる。
新しいスピリチュアリティ、意識の変容は、たいてい制度化された宗教の外で起こる。
思考と概念に支配されたこれまでの宗教でも、その一部には必ずささやかにスピリチュアリティが宿る場所があった(宗教組織はそれに脅威を感じ、多くの場合、抑圧しようとした)。
しかし宗教構造の外側で生じたスピリチュアリティの大きなうねりとなるとまったく新しい現象で、これまでは、とくに西欧では考えられなかった。
西欧文明はすべての文明のなかで最も理性を重視する文明だったし、
スピリチュアリティに関しては事実上キリスト教の教会による独占体制が確立していたからだ。
教会の許しもなくいきなり立ち上がってスピリチュアルな話をしたり、スピリチュアルな本を出版したりすることは不可能だったし、そんなことをしようものならたちまち沈黙させられただろう。
ところがいまでは教会や宗教のなかにも変化の兆しが現れている。
これは嬉しい兆候だ。ヨハネ・パウロ二世によるモスクやシナゴーグ訪問もささやかではあるが嬉しい開放への歩みだった。
既成宗教の外側で盛り上がってきたスピリチュアルな教えの影響に加え、古い東洋の智恵が流れ込んだことも大きな力となって、伝統的な宗教の信者にも形や教義、硬直した信念体系へのこだわりを捨て、スピリチュアルな伝統に隠されていた深さや自分自身の深さを発見する人たちが増えてきた。
この人たちは自分が「スピリチュアル」かどうかは何を信じているかではなく、どんな意識の状態にあるかによって決まることに気づいている。
そしてそれがその人の行動や人間関係を決定する。
形を超えた向こう側を見ることができない人たちは、自分の信念に、つまり自分のエゴイスティックな心にいっそう深く囚われてしまう。
現在、かつてなかった意識のうねりが見られるが、同時にエゴの壁も分厚く強化されている。
一部の宗教組織は新しい意識に向かって開かれるだろうが、さらに頑なに自分たちの立場や教義にこだわり、人間の集団的エゴの自衛と「反撃」の構造の一部になる宗教もあるだろう。
一部の教会、宗派、カルト、宗教運動は基本的には集団的エゴで、自分たちの主義主張に頑固にしがみつく。
現実に対する別の解釈を認めない閉鎖的な政治イデオロギーの信奉者と少しも変わらない。
だが、エゴは解体される運命にある。
その硬直化した構造は、宗教であれその他の制度、企業、政府であれ、一見どれほど強固に見えようとも内側から崩れていくだろう。
いちばん硬直した、いちばん変化しにくい構造がまず崩壊する。
ソ連の共産主義が良い例で、どれほど頑固に守りを固め、どれほど頑強な一枚岩に見えたかしれないが、ほころびが見えたほんの数年で内部から崩壊してしまった。
しかも、誰もその崩壊を予測できなかった。
すべてが突然で、誰もが驚いた。
このような驚きがこれからもたくさん、私たちを待っているはずだ。
変容の緊急性
古い生き方や相互関係、自然との関わりがうまくいかなくなり、根源的な危機が起こって、どうにも解決不可能と見える問題によって生存が脅かされると、個々の生命体――あるいは種――は死ぬか、絶滅するか、進化の飛躍によって置かれた条件の限界を乗り越える。
地球の生命体はまず海で進化したと考えられている。
地上にまったく動物がいなかったころ、海のなかには生命があふれていた。
それからいずれかの時点で、海の生物のあるものが乾いた地上への進出という冒険を余儀なくされた。
たぶん最初はほんの数センチ這い上り、巨大な重力にへとへとになって、重力をほとんど感じず楽に生きられる水中に戻ったのだろう。
だが再び地上への進出を試み、また試み、何度も試み続けて、やがて地上の生活に適応し、ひれの代わりに足が生え、えらの代わりに肺が発達する。
よほどの危機的状況に突き動かされなければ、種がこんな不慣れな環境に挑んで進化上の大変化を遂げるとは考えられない。
海の一部が大洋から切り離され、何千年かかけて徐々に干上がっていって、魚は生息地を離れて進化するしかなかったのかもしれない。
生存を脅かす根源的な危機に対処する――これがいま、人頬に突きつけられた課題である。
すでに二千五百年以上も前に古代の智恵ある教師たちが見抜いていた、そしていまは科学技術の発達によってますます拡大されつつある、人間のエゴイスティックな思考に固有の機能不全、これが初めて地球上の生命の存続を脅かしている。
ごく最近までは――これも古代の教師たちが指摘していた――人間の意識の変容はただの可能性にすぎず、ばらばらに離れたところで文化的宗教的な背景とは関わりなくごく少数の個人が実現しただけだった。
人類の意識の開花が広がらなかったのは、それほどの緊急性がなかったからだ。
地球上の相当数の人々が(まだ気づいていないとしても)まもなく気づくだろうが、人類はいま、進化するか死滅するかという重大な選択を迫られている。
そして古いエゴの思考パターンの崩壊と新たな次元の意識の芽生えを体験している人々はまだ比較的少数であるものの、その数は急激に増加しつつある。
いま生まれているのは、新しい信念体系でも新しい宗教やスピリチュアルなイデオロギーでも神話でもない。
神話だけではなくイデオロギーも信念体系も終わろうとしている。
変化は人々の心や思考よりも深いところで起こっている。
それどころか新しい意識の核心は思考の枠を超えることにある。
思考よりも高い場所に上り、思考よりもはるかに広い次元が自分自身のなかにあることに気づく新たな能力だ。
そのとき人は自分のアイデンティティを、自分が何者であるかの根拠を、いままで自分自身と同一視していた絶え間ない思考の流れには求めなくなる。
「自分の頭のなかの声」が実は自分ではないと気づくと、すばらしい開放感を味わう。
では自分とは何なのか?
自分とは、思考する自分を見ている者だ。
思考よりも前にある気づきであり、思考が――あるいは感情や知覚が――展開する場である。
エゴとは、形への自分の同一化にすぎない。
その形とは何よりも思考の形である。
悪に現実性があるとしたら――絶対的な現実性ではなく相対的な現実性だが――それもまた形(物理的な形、思考の形、感情の形)との全的な同一化と定義できる。
そのために、自分が全体とつながっていること、すべての「他者」及び「生命の源」と本質的に結びついていることをまったく認識できない。
この結びつきを忘れること、それが原罪であり、苦しみであり妄想なのだ。
この分離、分裂がすべての考え、言葉、行動の底流にあり、それらを律しているとしたら、人はどんな世界を生み出すか?
その答えを知るには人間同士の関わりを眺めれば、歴史書をひもとけば、あるいは今夜のテレビニュースを見ればいい。
人間の心の構造が変化しなければ、私たちはいつまでも基本的に同じ世界を、同じ悪を、同じ機能不全を繰り返し創造し続けるだろう。
新しい天と新しい地
本書のタイトルは聖書の預言からとっている。
人類史のなかで、いまほどこの預言がふさわしいことはないと思うからだ。
旧約聖書にも新約聖書にも、これまでの世界秩序の崩壊と「新しい天と新しい地」の誕生を預言する言葉がある。
ただしこの天とは空間的な場所のことではなく、内面的な意識の領域であることを理解しておかなければならない。
それがこの言葉の奥にある意味で、イエスも教えのなかでその意味で使っている。
これに対して地とは形の外的な現れであり、つねに内面を反映している。
人類の集団的な意識と地球の生命は本質的につながっている。
「新しい天」とは人類の意識の変容の始まりのことで、「新しい地」とはその変容が反映される物理的な領域のことだ。
人類の生命と意識は本質的に地球の生命と結びついているから、古い意識が解体すれば、それと呼応して地球の多くの場所で地理的にも気候的にも自然に大きな変化が起こる。
その一部を私たちはすでに目にしている。