「ニュー・アース―意識が変わる 世界が変わる―」(サンマーク出版)
エックハルト・トール(著),吉田 利子(翻訳)
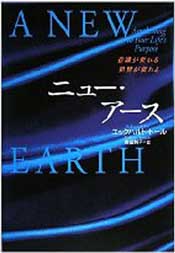
第2章 エゴという間違った自己のメカニズム
世界をありのままに見る
言葉は発音されても、あるいは声にならず思考に留まっても、ほとんど催眠術のような力を及ぼす。
言葉の前で人は簡単にわれを失い、何かに言葉を貼りつけたとたんに、まるで催眠術にかかったように、それが何であるかを知ったと思い込む。
ところが実際には、対象が何であるかなどわかっていない。
ただ、謎にラベルを貼っただけだ。小鳥も樹木も、そのへんの石ころでさえ、ましてや人間を究極的に知ることはできない。
計り知れない深さをもっているからだ。
私たちが感知し、経験し、考えることができるのは現実の表層だけで、海に出た氷山の一角よりも小さい。
その表面的な見かけの奥ではすべてが全体とつながりあっているだけでなく、すべてが拠ってきた「生命の源」とつながっている。
石ころでさえ、花や小鳥ならなおさらのこと、「神」へ、「生命の源」へ、あなた自身へと戻る道を示すことができる。
相手に言葉を付与したり、頭のなかでラベルを貼ったりせず、ただ手にとって、ありのままを見つめれば、驚異と畏敬の念が湧き起こるだろう。
対象の本質が無言のうちにあなたに語りかけ、あなたの本質を照らし出す。
偉大な芸術家が感じ取り、作品を通して伝えるのはこの本質だ。
ファン・ゴッホは「あれはただの古椅子だ」とは言わなかった。
彼は見て、見て、見つめた。
その椅子の存在を感じ取った。
それからカンバスの前に座り、絵筆をとった。
椅子そのものは数ドル程度のものだったかもしれない。
だが、その椅子の絵にいまでは二千五百万ドルの値がつく。
言葉やラベルを貼りつけないで世界をありのままに見れば、はるか昔に人類が思考を使うのではなく思考に縛られたときに失った奇跡のような畏敬の念が起る。
人生に深さが戻ってくる。
ものごとは再び初々しさ、新鮮さを取り戻す。
最大の奇跡は自己の本質を経験できることだ。
その本質は言葉や思考や知的なラベルやイメージに先行する。
それを経験するためには、「自分(I)」という意識、「在る(Beingness)」という意識を、自分と混同されているすべて、自分を同一化しているすべてから切り離さなくてはならない。
自分をモノや事物から切り離すこと、それが本書のテーマである。
ものごとや人や状況に、言葉や知的なラベルを急いで貼りつければ貼りつけるほど、あなたの現実は生命力を失って浅薄になり、現実を生き生きと感じ取れなくなって、あなた自身の内側や周囲で展開されている生命の奇跡に対する感覚が鈍くなる。
小賢しさは身についても智恵は失われ、喜びや愛や創造性や生き生きした躍動感もなくなる。
認識と解釈という生気のない状況のなかで消えてしまう。
もちろん私たちは言葉や思考を使う必要がある。
言葉や思考にはそれぞれの美がある――だがそこに囚われてしまう必要があるだろうか――言葉はものごとを頭で把握できる程度に簡略化する。
言語はaeiouの五つの母音と、空気圧の調節によって発音されるsfgその他の子音とでできている。
こんなシンプルな音の組み合わせだけであなたが何者なのか、宇宙の究極の目的とは何なのかを、いや樹木や石ころについてすら、その深みまで余すところなく説明できるなどと信じられるだろうか?
幻の自己
「私(I)」という言葉は、使い方しだいで最も大きな誤りを引き起こすことも最も深い真実を表すこともある。
ふつうの意味では、この言葉は(派生語の「私に(me)」「私の(my)」「私のもの(mine)」「私自身(myself)」などとあわせて)使用額度がいちばん高いだけでなく、最も誤解を生みやすい。
日常的な使い方の「私(I)」には根源的な誤りがあり、あなたが何者であるかを誤解させ、ありもしないアイデンティティを意識させる。
この幻の自己意識は、時空の現実だけでなく人間性についても深い洞察力を有していたアルバート・アインシュタインが「意識の光学的幻」と呼んだものだ。
この幻の自己意識がその後のあらゆる解釈の、というよりも現実に対する誤解のベースになり、すべての思考プロセスへ相互作用、関係性に影響する。
あなたの現実はこの根本にある幻を反映する。
ところで、良い知らせがある。
幻は幻と認識すれば消える、ということだ。
幻の認識はまた幻の終わりでもある。
あなたがそれを現実と誤解しているあいだだけ、幻は存続する。
自分が何者でないかを見きわめるなかから、自ずと自分は何者かという現実が立ち現れる。
私たちがエゴと呼ぶ間違った自己のメカニズムについて説明する本章と次章をゆっくり慎重に読み進んでくだされば、そうなるはずだ。
それでは幻の自己とはどんなものなのか?
あなたがふつうに「私(I)」と言うときに想定しているのは、ほんとうのあなたではない。
とんでもない単純化によって、無限の深さをもったあなたが「私(I)」という音声や頭のなかの「私(I)」という概念及びその中身と混同されるからだ。
それではふつうに言う「私(I)」やこれと関連する「私に(me)」「私の(my)」「私のもの(mine)」とは何を指しているのだろう?
両親が話す言葉を通じて幼児が自分の名前を覚えると、その名前(言葉)は幼児の頭のなかで一つの思考になり、それが自分と同一視される。
この段階では、子どもはよく「ジョニーはおなかがすいた」というように自分を三人称で表現する。
まもなく「私、僕(I)」という魔法の言葉を覚え、すでに自分自身と同一視している名前と同じように使いだす。
次に、他の思考がこの「私、僕(I)」という思考と混ざり合う。
この段階では「私、僕(I)」の一部とみなされるモノを指す「私の、僕の(my)」「私のもの、僕のもの(mine)」という思考がそれだ。
このモノと自分の同一化、つまりモノに(つきつめればモノが表している思考だが)自己意識をかぶせることによって、モノから自分のアイデンティティを引き出す。
「私の、僕の、おもちゃ(my)」玩具が壊れたり取り上げられたりすると、とてもつらい。
つらいのはその玩具自体がもっている価値のゆえではなく――幼児はすぐに興味を失って、他の玩具やモノに関心を移すだろう――「私のもの、僕のもの(mine)」という考えのゆえである。
玩具は幼児が発達させている「自己意識」「私、僕(I)」の一部になっていたのだ。
子どもが育つにつれ、「私、僕(I)」という思考は性別、持ち物、知覚される身体、国籍、人種、宗教、職業など、他の思考を引き寄せる。
他に「私、僕(I)」が同一視するのは――母親、父親、妻などの――役割、積み重ねられた知識や好悪などの意見、それに過去に「私に(me)」起こった出来事である(過去の出来事の記憶が『私と私の物語(me and my story)」として自己意識を規定する)。
これらは人がアイデンティティを引き出すものごとのほんの一部にすぎない。
そしてどれも、自己意識という衣を着せるという事実によって危なっかしくまとめあげられた思考以上のものではない。
ふつう「私、僕(I)」という場合に指しているのは、この精神的な構築物なのだ。
もっとはっきり言えば、あなたが「私、僕(I)」と言ったり考えたりするとき、だいたいはその主体はあなたではなく、この精神的な構築物すなわちエゴイスティックな自己のいずれかの側面である。
そこに気づいたあとでも、あなたはやはり「私、僕(I)」という言葉を使うだろうが、そのときにはこの言葉はもっと深い部分から発することだろう。
ほとんどの人は依然として、絶え間ない思考の流れ(大半が無意味な繰り返しである)や衝動的思考に自分を完全に同一化している。
この思考プロセスとそれに付随する感情から離れて「私、僕(I)」は存在しない。
これはスピリチュアルな無自覚状態を意味する。
頭のなかには片時も止まらずにしゃべり続けている声があると言われると、人は「それはどんな声か?」と聞き返したり、そんなことはないとむきになって否定する。
聞き返したり、むきになったりするのはもちろん、その声、考えている無意識な心だ。
それが人々を乗っ取っていると見ることもできる。
自分の思考と自分自身とを切り離し、一瞬であっても、考えている心からその背景にある気づきに自分自身のアイデンティティが移行したことがある人は、その体験を決して忘れない。
またアイデンティティの移行が非常に微妙だったためにほとんど気づかなかったり、理由はわからないままに喜びや内面的な安らぎだけを感じ取る人もいる。
頭のなかの声
私が初めてアイデンティティの移行を体験したのは、ロンドン大学の学生のときだった。
週に二度、通常はラツシュが終わった午前九時ごろに地下鉄で大学の図書館に行くのが習慣になっていた。
あるとき地下鉄で、三十代はじめとおぼしき女性が向かいに座った。
それまでも数回、見かけたことがある女性だった。
誰もがその女性には気づいたはずだ。
地下鉄は満員だったのに彼女の両隣には誰も座らない。
理由は、彼女がどうも正気には見えなかったからだ。
何やらいきりたって不機嫌な声を張り上げ、休みなく独り言を言っている。
自分の頭のなかの考えに夢中で、まわりの人々にも状況にもまったく気づいていないらしい。
左斜め下に目をやって、空っぽの隣席の誰かに話しかけているかに見えた。
こんな調子だった。
「そうしたら彼女が私に言ったの・・・だから、嘘つき、よく私が悪いなんて言えるわねって言い返したわよ・・・いつだって私を利用するのはあなたじゃないの、私は信用していたのに、あなたはその信用を裏切ったんじゃない・・・」。
不当に扱われて、なんとか反論しなくてはいけない、さもないと自分がつぶされるという怒りがその声から伝わってきた。
地下鉄がトツテナム・コート・ロード駅に近づくと、女性は立ち上がってドアのほうへ行ったが、あいかわらず独り言を続けている。
私が降りる駅も同じだったから、彼女のあとに続いた。
駅を出ると彼女はベッドフォード・スクエアに向かって歩き出したが、なおも想像上の対話を続け、怒った調子で誰かを非難し反論していた。
私は好奇心に駆られ、方向が同じあいだはあとをつけてみようと思った。
想像上の対話に没頭しながらも、彼女にはちゃんと行く先がわかっているらしく、まもなく大学本部と図書館がある一九三〇年代に建てられたセネート・ハウスの堂々たる姿が見えてきた。
私は驚いた。
もしや、彼女は私と同じところを目指しているのか?
そう、確かに彼女はセネート・ハウスに向かっていた。
教員か学生か、あるいは事務員か司書なのか?
それとも心理学者の調査プロジェクトの被験者?
答えはわからなかった。
二十歩ほど後ろを歩いていた私が、建物(皮肉なことに、ここはジョージ・オーウェルの一九八四年」が映画化されたときに「思想警察」本部のロケ地となった)の入り口に達したとき、もう彼女はエレベーターの一つに乗り込んだあとだった。
私はいま目撃したことに衝撃を受けていた。
二十五歳でそれなりに成熟した大学生だったから、自分は知的な人間だと思っていたし、人間存在のジレンマに対する答えはすべて知性を通じて、つまり思考によって見出すことができると信じて疑わなかったのだ。
気づきのない思考こそが人間存在の主たるジレンマであることをまだ悟っていなかった。
教授陣はすべての答えを知っている賢者で、大学は知識の殿堂だと振り仰いでいた。
あの女性のような正気とは思えない人がその大学の一部だなんてことがあるだろうか?
図書館に行く前にトイレに入ったときも考え込んでいた。
手を洗いながら、あんなふうになったらおしまいだよな、と思った。
すると隣にいた男性がちらっとこちらを見た。
私は思っただけでなく口に出していたことに気づいて愕然とした。
なんてことだ、もうすでに同じだ。
自分も彼女と同じように絶え間なく心のなかでしゃべり続けていたのだろうか?
私と彼女にはわずかな違いしかなかった。
彼女の思考に圧倒的な優位を占めているのは怒りらしいが、私の場合は不安、それだけだ。
彼女は考えを口に出し、私は――たいていは――頭のなかで考えている。
もし彼女が異常なら、私を含めて誰でも正気を逸している。
程度の違いでしかない。
一憐、私は自分の心から離れて、いわばもっと深い視点から自分を見ていた。
思考から気づきへの瞬間的な移行だった。
私はまだトイレにいたが、他にはもう誰もいなかったので、鏡に映る自分の顔を見つめた。
そして自分の心から離れたその一瞬に、声を上げて笑ったのだ。
狂気じみた笑いに聞こえたかもしれないが、それは正気の笑い、恰幅のいいブツダの笑いだった。
「人生なんて、お前の心が思い込みたがるほど深刻なものじゃないよ」。
その笑いはそう言っているようだった。
だがそれもほんの一瞬のことで、たちまち忘れ去られた。
それから三年間を私は不安な鬱々とした気分で、思考する心に自分を完全に同一化して過ごした。
気づきが戻ってきたのは自殺の瀬戸際まで行ったあとのことだったが、今度の気づきはつかの間で消えはしなかった。
私は衝動的な思考と心が創り出した間違った自己意識から解放された。
前述の出来事で私は初めて気づきを垣間見ただけでなく、人間の知性の絶対的な有効性に対する疑念を初めて植えつけられた。
それから数か月して、この疑念をますます強める悲劇的な事件が起こった。
月曜日の朝、深く敬愛していた教授の講義に出たところ、教授は週末に銃で自殺したと知らされたのだ。
私は仰天した。
大変尊敬されている、そしてすべての答えを知っているかに見えた教授だった。
だが私はまだ、思考を培う以外の選択肢を見つけることができなかった。
思考は意識のほんの小さな側面でしかないことに気づかず、エゴについて何も知らなかったし、ましてやそれを自分のなかに見抜くことなどできはしなかったからだ。
エゴの中身と構造
エゴイスティックな心は完全に過去によって条件づけられている。
その条件づけは二つの面から行われる。
中身と構造である。
玩具を奪われて泣く子どもの場合、この玩具はエゴイスティックな心の中身にあたる。
これは他のどんな内容でも、どんな玩具やモノでも代替可能だ。
あなたのアイデンティティの中身は環境や育ち、文化によって条件づけられる。
子どもが豊かでも貧しくても、動物に似た木切れの玩具でも精密な電子玩具でも、なくしたときの苦しみという点では同じだ。
どうしてそんな苦しみが生じるか、その理由は「私の、僕の(my)」という言葉に隠されている。
これが構造である。
モノとの結びつきによって自分のアイデンティティを強化したいという無意識の衝動は、エゴイスティックな心の構造にしっかりと組み込まれている。
エゴが生まれる最も基本的な精神構造の一つがアイデンティティである。
「アイデンティフィケ-ション(同一化)」という言葉の語源は、「同じ」という意味のラテン語idemと、「作る、為す」という意味のfacereだ。
何かにアイデンティティを求める、同一化するというのは、「それを同じだとする」という意味なのだ。
何と同じだとするのか?
「私(I)」である。
私はそれに自己意識を付与し、それが私の「アイデンティティ」の一部になる。
最も基本的なレベルでのアイデンティティの対象はモノだ。
私の、僕の玩具はいずれ私の車、私の家、私の衣服などになる。
私はモノに自分自身を見出そうとするが、しかし完全に同一化しきってそこに投入することはできない。
それがエゴの運命なのだ。
アイデンティティとしてのモノ
広告業界の人間は、ほんとうは必要ないモノを売りつけるためには、それをもっていると自己イメージが、あるいは他者から見たイメージが変化すると消費者に思わせなければならないと知っている。
言い換えれば、自己意識に何かを付け加えられます、ということだ。
たとえばこの製品を使っているとひときわ目立ちます、だからもっとあなたらしくなれますよ、と言う。
あるいは製品から有名人を、それとも若くて魅力的で幸せそうな人間を連想するように仕向ける。
昔の人や故人となった有名人の最盛期の姿でもかまわない。
このとき無言のうちに想定されているのは、この製品を買えば不思議な作用が働いてあなたは彼らのようになれる、もしくは彼らのイメージとそっくりになれる、ということだ。
だから多くの場合、人は製品を買うのではなくて「アイデンティティの強化」を買う。
デザイナーズブランドは集団的アイデンティティの最たるものである。
デザイナーズブランドの製品は高価だから「排他的」だ。
誰でももっていたのでは心理的な価値はなくなり、残るのは物質的価値だけになる。
それは値段のほんの一部でしかないだろう。
何にアイデンティティを感じるかは、人によって、年齢や性別や所得、社会階層、流行、文化などによって大きく異なる。
そして何にアイデンティティを感じるかは、エゴの中身と関係する。
それに対して何かにアイデンティティを求めたいという無意識な衝動は、エゴの構造のほうと関係している。
エゴイスティックな心の最も基本的な作用の一つだ。
逆に、いわゆる消費社会が成り立つのは、人がモノに自分自身を見出そうとする努力がどうしてもうまくいかないからである。
エゴの満足は長続きしないから、さらに多くを求めて買い続け、消費し続けなければならない。
もちろん私たちの表面的な自己が生きている物理的な次元ではモノは必要だし、暮らしに不可欠である。
住まいも衣服も家具も道具も乗り物も必要だ。
それに美や固有の質のゆえに高く評価されるものもあるだろう。
私たちはモノの世界を毛嫌いするのではなく、尊重しなければならない。
モノはそれぞれ、すべてのものや身体や形の根源である、形のない「生命」に起源をもつ一時的な存在としてあるのだから。
古代の人々は無生物も含めたすべてに霊が宿ると信じていた。
この点では彼らのほうが現代人より真実に近い。
概念化や抽象化で生気を失った世界に暮らしていると、もはや生き生きした宇宙を感じられなくなる。
いまほとんどの人は現実に生きているのではなく、概念化された現実を生きている。
だがモノを自己意識強化の手段に使う、つまりモノを通じて自分自身を発見しようとするのは、ほんとうにモノを尊重することではない。
エゴがモノに同一化しようとするとモノへの執着や強迫観念が生まれ、そこから進歩の唯一のものさしがつねに「より多く」である消費社会と消費構造が生まれる。
これは自己を増殖させることだけが目的であって、実は自分がその一部である組織体を破壊し自分も破壊する結果になると気づかないガン細胞と同じ機能不全である。
エコノミストの中には成功という考え方に執着するあまり、どうしてもこの言葉を使わずにはいられない人たちがいて、不景気を「マイナス成長」と称したりする。
多くの人々はモノに対する強迫的な先入観に生活の大部分を支配されている。
だからモノの増殖が現代の病弊の一つになる。
自分を生き生きした生命体として感じられなくなると、人はモノで人生を満たそうとする。
スピリチュアルな実践として自分を振り返り、モノの世界との関係、とくに「私の(my)」という言葉を付されるモノとの関係を見直してみることをお勧めする。
たとえば自尊心が所有物と結びついているかどうかを判断するには、注意深くて正直でなければならない。
あるモノをもっているというだけで、なんとなく自分が重要人物だとか優れた人間だと感じないか?
何かが欠けていると、たくさん所有している人に劣等感を感じないか?
他人の目や他人の目を通じて自分自身に映る自分の価値を引き上げるために、さりげなく自分の所有物をほのめかしたり、見せびらかしたりはしないか?
誰かがあなたより多くをもっているとき、あるいは大事なものをなくしたとき、恨みや怒りを感じ、自分が小さくなったように感じることはないか?
なくなった指輪
スピリチュアルな問題について指導するカウンセラーとして、ある女性ガン患者のもとへ週に二度ずつ通っていたことがある。
その女性は四十代の教員で、医師から余命数か月と宣告されていた。
訪ねていって数語交わすこともあれば、黙ってただ一緒に座っていることもあった。
そのとき彼女は初めて自分のなかにある、忙しい教師時代には存在すら知らなかった静謐(せいひつ)さを垣間見たのだった。
ところがある日訪ねてみると、彼女はひどくがっかりし、怒っていた。
「何があったのですか?」と尋ねたところ、ダイヤの指輪がなくなったという。
金銭的な価値もさることながら、とても思い出深い品だった。
きっと毎日数時間、世話をしにくる女性が盗んだに違いない。
病人に対してよくもそんな無神経なひどいことができるものだ、と彼女は言った。
そしてその女性を問いただすべきか、それともすぐに警察に通報したほうがいいか、と私の意見を求めた。
どうすべきか指図はできないと答えたが、しかし指輪であれどんな品物であれ、いまのあなたにとってどれほど重要なのかを考えてみてはどうか、と私は助言した。
「あなたにはおわかりにならない」と彼女は言い返した。
「あれは祖母からもらった指輪でした。毎日はめていたのだけれど、病気になって手がむくんではめられなくなったんです。
あれはただの指輪じゃない。騒ぎ立てるのも当然じゃないですか、そうでしょう?」。
その返事の勢いや声にこもる怒りと自己防衛の響きは、彼女がまだ充分に「いまに在る」心境になれず、起こった出来事と自分の反応を切り離して別々に観察するに至っていないことを示していた。
怒りと自己防衛は、まだ彼女を通じてエゴが発言しているしるしだった。
私は言った。
「それじゃ、いくつか質問をします。
すぐに答えなくていいですから自分の中に答えが見つかるかどうか探してみてください。
質問ごとに、少し間をあけますからね。
答えが浮かんでも、必ずしも言葉にしなくてもいいんですよ」。
どうぞ、聞いてください、と彼女は言った。
「あなたはいずれ、それもたぶん近いうちに指輪を手放さなくてはならないことに気づいていますか?
それを手放す用意ができるまで、あとどれほどの時間が必要でしょう?
手放したら、自分が小さくなりますか?
それがなくなったら、あなたは損なわれますか?」。
最後の質問のあと、しばらく沈黙があった。
再び話し始めたとき、彼女の顔には安らかな笑みが浮かんでいた。
「最後の質問で、とても大切なことに気づきました。
自分の心に答えを聞いてみたら、こういう答えが返ってきたんです。
そりゃ、もちろん損なわれるわ。
それからもう一度、問い返してみました。
私は損なわれるだろうか?」。
今度は考えて答えを出すのではなく、感じてみようとしました。
そうしたらふいに、「私は在る、と感じることができたのです。こんなふうに感じたのは初めてだわ。
こんなに強く自分を感じられるなら、私はまったく損なわれてはいないはず。
いまでもそれを感じられる。穏やかだけれど、とても生き生きとした自分を感じられます」。
「それが『大いなる存在』の喜びですよ」と私は言った。
「頭から抜け出したときに、初めてそれを感じられるんです。
それは感じるしかない。
考えたってわかりません。
エゴはそれを知らない。
だってエゴは思考でできていますからね。
その指輪は実は思考としてあなたの頭のなかにあり、それをあなたは自分と混同していたんですよ。
あなたは自分あるいはその一部が指輪のなかにあると考えていた。
エゴが求め執着するのは、エゴが感じることができない『大いなる存在」の代用品です。
モノを評価して大切にするのはいいが、それに執着を感じたら、それはエゴだと気づかなくてはいけません。
それにほんとうはモノにではなく、モノにこめられた『私(I)』『私の(my)』『私のもの(mine)』という思考に執着しているのです。
喪失を完全に受け入れたとき、あなたはエゴを乗り越え、あなたという存在が、『私は在る』ということが、つまり意識そのものが現れるのです」。
彼女は言った。「いまようやく、これまでどうしてもわからなかった「下着を取ろうとする者がいたら、上着も与えなさい」というイエスの言葉の意味が理解できました」。
「その通りです」。私は答えた。
「その言葉は、決してドアに鍵をかけるな、という意味じゃありません。
ときにはモノを手放すほうが、守ったりしがみついたりするよりもはるかに力強い行いだ、という意味なんですよ」。
身体がますます衰弱していった最後の数週間、彼女はまるで光が内側から輝き出しているように明るかった。
いろいろな人にたくさんのモノを分け与えたが、そのなかには指輪を盗んだと疑った女性も入っていた。
そして与えるたびに、彼女の喜びはますます深くなった。
彼女の死を知らせてきた母親は、亡くなったあとで例の指輪がバスルームの薬品戸棚で見つかったと言った。
手伝いの女性が指輪を返したのか、それともずっとそこに置き忘れられていたのか?
それは誰にもわからない。
だがわかっていることが一つある。
人生は意識の進化に最も役立つ経験を与える、ということだ。
いまの経験が自分に必要だとどうしてわかるのか?
それは現にこの瞬間に体験しているからだ。
自分の所有物に誇りをもったり、自分より豊かな人をうらやんだりするのは間違っているのか?
そんなことはない。
誇りや目立ちたいという思いや、「もっと多く」によって自己意識が強化され、「より少なく」によって自分が小さくなると感じるのは、善でも悪でもない。
エゴだというだけである。
エゴは悪ではない。
ただの無意識だ。
自分のなかのエゴを観察するとき、エゴの克服が始まる。
エゴをあまり深刻に受け取らないほうがいい。
自分のなかにエゴの行動を発見したら、微笑もう。
ときには声を出して笑ってもいい。
人間はどうしてこんなものに、これほど長くだまされ、囚われていたのか?
何よりも、エゴは個人ではないことに気づくべきだ。
エゴはあなたではない。
エゴを自分個人の問題だと考えるならば、それもまたエゴなのだ。
所有という幻
何かを「所有する」、これはほんとうは何を意味しているのだろうか?
何かを「自分のもの(mine)」にするとは、どういうことなのか?
ニューヨークの街頭に立って摩天楼の一つを指差し、「このビルは私のものだ。私が所有している」と叫んだとしたら、あなたはとてつもなく金持ちか、妄想を抱いているか、嘘つきだ。
いずれにしてもあなたは一つの物語を語っているのであり、そのなかでは「私」という思考の形と「建物」という思考の形がひとつに溶け合っている。
所有という概念はそういうことだ。
誰もがあなたの物語に同意するなら、所有を証明する書類が存在するだろう。
あなたは大金持ちだ。
誰も同意してくれないなら、あなたは妄想患者か虚言症かもしれないということで精神科医のもとへ送られるだろう。
大切なのは、人が物語に同意してくれようとくれまいと、物語と物語を形成している思考の形は実はあなた自身とは何の関係もない、と認識することだ。
たとえ人が同意してくれても、結局は物語、フィクションであることに変わりはない。
多くの人は、死の床に就き外部的なものがすべてはげ落ちて初めて、どんなモノも自分とは何の関係もないことに気づく。
死が近づくと、所有という概念そのものがまったく無意味であることが暴露される。
さらに人は人生の最後の瞬間に、生涯を通じて完全な自己意識を求めてきたが、実は探し求めていた「大いなる存在としての自分」はいつも目の前にあったのに見えなかった、それはモノにアイデンティティを求めていたからで、つきつめれば思考つまり心にアイデンティティを求めていたからだ、と気づく。
「心の貧しい者は幸いです」とイエスは言った。
「天の御国はその人のものだからです」と。
「心の貧しい」とはどういうことか?
心に何の持ち物もない、何にも自分を同一化(アイデンティファイ)していない、ということだ。
そういう人はどんなモノにも、また自己意識と関係するどんな概念にも、アイデンティティを求めていない。
それでは「天の御国」とは何か?
それはシンプルな、しかし深い「大いなる存在」の喜びのことだ。
その喜びは、何かに自分を同一化するのをやめて、「心の貧しい者」になったときに感じることができる。
だからこそ、東洋でも西洋でも古くからのスピリチュアルな実践で、あらゆる所有が否定されてきた。
しかし所有を否定しても、それだけでエゴから解放されるわけではない。
エゴは何か別のものに、たとえば自分は物質的所有への関心を乗り越えた優れた人間だ、人よりもスピリチュアルなのだという精神的な自己イメージにアイデンティティを求めて生き延びようと図るだろう。
すべての所有を否定していながら、億万長者よりも大きなエゴをもった人たちがいる。
一つのアイデンティティを取り払うと、エゴはすぐに別のものを見つけ出す。
要するにエゴは何にアイデンティティを求めようとかまわない、自分を同一化(アイデンティファイ)するものが何かあればいいのだ。
消費文明批判や財産の私有制度反対も一つの思考、精神的な所有物で、所有そのものに代わるアイデンティティになり得る。
そのアイデンティティを通じて、自分は正しくて他者は間違っていると考えることができる。
あとで取り上げるが、自分は正しく他者は間違っているという考えはエゴイスティックな心の主たるパターンの一つ、無意識の主たる形の一つだ。
言い換えれば、エゴの中身は変わってもそれを生かしておく構造は変わらない。
これに関係して無意識に想定されているのが、所有というフィクションを通じてモノに自分を同一化すると、物質がもっているかに見える堅実性や恒久性のおかげで自分にも大いなる堅実性や恒久性が付与されるはずだということだ。
建物なんかはとくにそうだし、もっと都合がいいのは破壊することのできない唯一の所有物である土地だろう。
土地の場合は、所有ということの馬鹿馬鹿しさがとりわけあらわになる。
白人入植者が侵入してきたとき、北米先住民は土地所有という考え方を理解できなかった。
だからヨーロッパ人に、これも同じく理解を超えた書類に署名させられて土地を失った。
彼らは土地が自分たちに属しているのではなく自分たちが土地に属しているのだと感じていたのである。
エゴはまた所有と「大いなる存在」を同一視する傾向がある。
われ所有す、ゆえにわれ在り、というわけだ。
そして多くを所有すればするほど、自分の存在も豊かになる、と考える。
エゴは比較のなかに生きている。
私たちは、他人にどう見られているかで、自分をどう見るかを決める。
誰もが豪邸に住んで誰もが豊かなら、豪邸も富も自己意識を高めるのには役立たない。
それなら粗末な小屋に住み、富を放棄して、自分は他人よりスピリチュアルだと思うことで、自分のアイデンティティを取り戻すことができる。
他人にどう見られるかが、自分はどういう人間か、何者なのかを映し出す鏡になるのである。
エゴの自尊心は多くの場合、他者の目に映る自分の価値と結びついている。
自己意識を獲得するには他者が必要なのだ。
そして何をどれくらいもっていると見抜けない限り、自尊心を求め自己意識を充足させようとしてむなしい希望に振り回され、一生、モノを追い求めることになる。
モノに対する執着を手放すにはどうすればいいのか?
そんなことは試みないほうがいい。
モノに自分を見出そうとしなければ、モノへの執着は自然に消える。
それまでは、自分はモノに執着していると気づくだけでいい。
対象を失うか失う危険にさらされなければ、何かに執着している、つまり何かと自分を同一化していることがわからないかもしれない。
失いそうになってあわてたり不安になるなら、それは執着だ。
モノに自分を同一化していると気づけば、モノへの同一化は完全ではなくなる。
「執着に気づいている、その気づきが私である」。
それが意識の変容の第一歩だ。
欲望:もっと欲しい
エゴは所有と自分を同一化するが、所有の満足は比較的薄っぺらで短命だ。
そこに隠れているのは根深い不満、非充足感、「まだ充分じゃない」という思いである。
エゴが「私はまだ充分にもっていない」というのは、「私はまだ充分じゃない」ということなのだ。
これまで見てきたように、何かをもっている――所有――という概念は、エゴが自分に堅実性と恒常性を与え、自分を際立たせ、特別な存在にするために創り出したフィクションである。
だが所有を通じて自分を発見することは不可能だから、その奥にはエゴの構造につきものの「もっと必要だ」というさらに強力な衝動が存在する。
これが「欲望」である。
エゴは、もっと必要だという欲求なしに長いあいだ過ごすことはできない。
だからエゴを存続させているのは所有よりもむしろ欲望だ。
エゴは所有したいという以上に欲したいと願う。
だから所有がもたらす薄っぺらな満足はつねに、もっと欲しいという欲望にとって代わられる。
もっと欲しい、もっと必要だというのは、自分を同一化させるモノがもっと必要だという心理的な要求である。
ほんとうに必要なのではなくて、依存症的な要求なのだ。
エゴの特徴であるもっと欲しいという心理的な要求、まだ充分ではないという思いは、場合によっては肉体的なレベルに移行して飽くなき飢えとなる。
過食症患者は吐いてでも食べ続ける。
飢えているのは心であって、身体ではない。
患者が自分を心に同一化するのをやめて身体感覚を取り戻し、エゴイスティックな心を駆り立てる偽りの要求ではなく身体のほんとうの要求を感じるようになったとき、摂食障害は治癒する。
あるエゴは自分が欲するものを知って、冷酷に断固として目的を達成しようとする。
ジンギスカン、スターリン、ヒトラーなどはその並外れた例である。
だが彼らの欲望の奥にあるエネルギーは同じく強烈な反対方向のエネルギーを生み出し、結局は当人たちの破滅につながる。
そして他の多くの人も不幸にする。
前述の並外れた例で言えば、地上に地獄を生み出す。
ほとんどのエゴは矛盾する欲望をもっている。
また時が移れば欲望の対象が変化する。
欲しいのはいまあるものではない、つまりいまの現実ではないということがわかっているだけで、実は何が欲しいのかわからなかったりする。
苛立ち、焦燥感、退屈、不安、不満は、満たされない欲望の結果だ。
欲望は構造的なものだから、精神的な構造が変わらない限り、内容がどうであろうと永続的な満足はあり得ない。
具体的な対象のない強烈な欲望はまだ発達段階にある十代の若者によく見られ、なかにはいつも暗くて不満だらけどいう者もいる。
もっと多く欲しいという飽くことを知らない要求、つまりエゴの食欲さは地球の資源とつりあいが取れない。
このアンバランスさえなければ、地球上の全人口の食物、水、住まい、衣服、基本的快適さなどの物理的な要求は簡単に満たすことができるだろう。
エゴの食欲さは世界の経済構造、たとえばもっと多くを求めて争いあうエゴイスティックな存在である大企業などに集団的に現れている。
企業はひたすら儲けることだけを目的としている。
なりふりかまわず容赦なく営利という目的を追求する。
自然も動物も人々も、自社の社員さえも、企業にとっては貸借対照表の数字、使い捨てのできる生命のないモノにすぎない。
「私に(me)」「私のもの(mine)」「もっと(more than)」「欲しい(I want)」「必要だ(I need)」「どうしても手に入れる(I must have)」「まだ足りない(not enough)」というような思考の形は、エゴの内容ではなくて構造に付随する。
エゴの内容、同一化の対象は変わっていくだろう。
自分自身のなかにあるこの思考の形に気づかない限り、それらが無意識に留まっている限り、あなたはエゴの言葉を信じてしまう。
無意識の思考を行動化し、見つからないものを求め続ける運命から逃れられない。
なぜならこのような思考の形が作用している限り、どんな所有物にも場所にも人にも条件にも満足できるはずがないからだ。
エゴの構造がそのままである限り、あなたはどんな内容にも満足できない。
何をもっていようと、何を手に入れようと幸せにはなれない。
いつももっと満足できそうな他の何かを、不完全な自分を完全だと思わせ内部の欠落感を満たしてくれるはずの何かを、探し求めずにはいられない。
身体との同一化
モノ以外に自分を同一化させる基本的な対象は「私の(my)」身体だ。
身体はまず男か女だから、ほとんどの人の自己意識のなかでは男性であるか女性であるかが大きな部分を占める。
その性別がアイデンティティになる。
自分の性別への同一化は幼いころから促され、役割意識が植えつけられ、性的な面だけでなく生活のすべてに影響する行動パターンを条件づけられる。
多くの人たちは完全にこの役割に囚われているが、性別に関する意識が多少とも薄れかけている西欧より一部の伝統的な社会のほうがその傾向はいっそう強い。
そのような伝統的な社会では、女性にとっては未婚や不妊が、男性にとっては性的能力の欠落と子どもをもうけられないことが最悪の運命となる。
満たされた人生とは性別というアイデンティティを充足することだとみなされる。
西欧では物理的外見的な身体が、つまり他人と比較して強いか弱いか、美しいか醜いかが自意識に大きな影響を及ぼす。
多くの人々の自尊心は肉体的な力や器量、容姿、外見などと強く結びついている。
身体が醜いとか不完全だと思うために自尊心が萎縮して傷ついている人たちは多い。
本人が「自分の身体」にもつイメージや概念がまったく歪んでいて、現実とかけ離れていることもある。
若い女性がほんとうは痩せているのに太りすぎだと思うと、餓死しかねないほどのダイエットを強行する。
そういう女性にはもう自分の身体が見えていない。
彼女たちが「見て」いるのは身体に関する概念だけで、それが「私は太っている」あるいは「太りかけている」と告げる。
このような状態の底には心への自分の同一化がある。
この数十年、人々がますます自分を心に同一化させ、エゴの機能不全が強くなって、拒食症が劇的に増加した。
拒食症患者が心というおせっかいな判定者なしに自分の身体を見られれば、あるいはその判定者の言葉を信じ込む代わりにその正体に気づきさえすれば――自分の身体をきちんと感じ取れればもっといい――拒食症は快方に向かうだろう。
美しい容貌や肉体的な力、能力などと自分を同一化している人は、そういう資質が(当然のことながら)衰えて消えていくと苦しみを味わう。
それらの資質に上るアイデンティティそのものが崩壊の危機にさらされるからだ。
醜くても美しくても、つまりマイナスでもプラスでも、人はアイデンティティのかなりの部分を身体から引き出している。
もつと正確に言えば、自分の身体に関する精神的なイメージや概念を間違って自分だと思い込み、その思考に自分を同一化しているが、実は身体も他の物理的な形態と同じで、すべての形がもつ一時的なもので結局は滅びるしかない――運命を分かち合っている。
知覚に感知される物理的な身体はいずれは老いて衰え、死ぬ運命にあるのに、その身体を自分と同一視すれば、遅かれ早かれきっと苦しむ。
身体にアイデンティティを求めないということは、身体を無視したり嫌悪したり、かまわずに放置することではない。
身体が強くて美しく、精力的ならば、その資質を――それが存続するあいだは――感謝して楽しめばいい。
さらに正しい食生活や運動で身体のコンディションを改善することもできる。
身体を自分と同一視していなければ、美貌が色あせ、精力が衰え、身体の一部や能力が損なわれても、自尊心やアイデンティティは影響されないだろう。
それどころか身体が衰えれば、衰えた身体を通して形のない次元が、意識の光がやすやすと輝き出るようになる。
完壁に近い優れた身体をもつ人々だけが身体と自分を同一視するわけではない。
人は「問題のある」身体にも簡単に自分を同一化し、身体の欠損や病気や障害をアイデンティティに取り込む。
そうなると自分は損傷や慢性的な病気や障害に「苦しんでいる者」だと考え、人にもそう語る。
そして障害に苦しむ者、患者という概念的なアイデンティティをつねに確認してくれる医師その他から多大の関心を獲得する。
するとみ意識のうちに疾病にしがみつく。
それが自分の考える「自分自身」、アイデンティティの最も重要な部分になるからだ。
それもエゴが自分を同一化する思考の形の一つである。
エゴは一度発見したアイデンティティは手放そうとしない。
驚くべきことだが、より強力なアイデンティティを求めて、エゴが疾病を創り出すことだって珍しくはない。
内なる身体を感じる
身体への同一化はエゴの最も基本的な形の一つだが、ありがたいことにこれは最も簡単に乗り越えられるアイデンティティでもある。
ただしそのためには、自分は身体ではないと自分に言い聞かせるのではなく、関心を外形的な身体や自分の身体に関する思考――美しい、醜い、強い、弱い、太りすぎ、痩せすぎ――から引き推して、内側から感じられる生命感に移す必要がある。
外形的な身体がどんなレベルにあろうとも、形を乗り越えたところでは身体は生き生きとしたエネルギーの場なのである。
内なる身体への気づきに慣れていないなら、しばらく目をつぶって自分の両手のなかに生命感を感じられるかどうか試してみるといい。
そのときは、心に聞いてはいけない。
心は「何も感じない」と答えるだろう。
さらには「もっとおもしろいことを考えたらどうだい」と言うかもしれない。
だから心に尋ねる代わりに、じかに両手を感じる。
つまり両手のなかのかすかな生命感を感じるのである。
生命感はそこにある。
それに気づくには、関心を向けさえすればいい。
最初はかすかなちりちりした感触かもしれないが、やがてエネルギーあるいは生命感を感じることができる。
しばらく両手に関心を集中していると、その生命感は強くなっていくだろう。
人によっては目を閉じる必要もないかもしれない。
この文章を読みながら、「内なる手」を感じられる人もいるだろう。
次に両足に関心を移動させてしばらくそこに留め、それから両手と両足を同時に感じてみる。
そのあとは身体の他の部分――腿(もも)、腕、腹、胸など――を付け加えていって、最後には内なる身体全体の生命感を感じ取る。
この「内なる身体」は、ほんとうは身体ではなくて生命エネルギーで、形と形のないものとの架け橋だ。
できるだけしょっちゅう、内なる身体を感じる習慣をつけるといい。
そのうち目を閉じなくても感じられるようになる。
ところでへ誰かの話を聞きながら内なる身体を感じることはできるだろうか。
逆説的ながら、内なる身体を感じているときには、実は自分を身体と同一化していない。
また心とも同一化していない。
要するにもう自分を「形」と同一化せず、形への同一化から形のないものへの同一化に移行している。
その形のないもの、それは「大いなる存在」と言ってもいい。
それがあなたのアイデンティティの核心である。
身体への気づきはいまこの瞬間にあなたをつなぎとめるだけでなく、エゴという牢獄からの出口でもある。
さらに免疫システムも、身体の自然治癒力も強化される。
忘れられる「大いなる存在」
エゴはいつも自分を形と同一化し、何らかの形に自分自身を求め、それゆえに自分自身を失う。
この形とは物質や肉体だけではない。
外部の形――モノや身体――よりもっと基本的なのが、意識の場につねに生起する思考の形だ。
これは形になったエネルギーで、物質よりももっと微妙で密度が薄いが、やはり形である。
気づいてみれば、片時もやまない頭のなかの声があるはずだ。
絶え間ない衝動的な思考の流れである。
その考えに関心をすべて吸い取られ、頭のなかの声やそれに付随する感情に自分を同一化してしまって、その思考や感情のなかで自分自身を失ったとき、そのときあなたは自分を形に完全に同一化してしまい、エゴの手中に落ちる。
エゴとは「自己」という意識、エゴという意識をまとって繰り返し生起する思考の形と条件づけられた精神・感情パターンの塊なのだ。
形のない意識である「大いなる存在(Being)」「私は在る(I am)」という感覚が形とごっちゃになったときに、エゴが生じる。
これが自分と個々の形との同一化(アイデンティフィケーション)ということだ。
つまり「大いなる存在」を忘れるという第一義的な誤りであり、存在が個々の形に分裂するというとんでもない幻想が、現実を悪夢に変える。
デカルトの誤りからサルトルの洞察へ
近代哲学の祖とみなされている十七世紀の哲学者デカルトは、この第一義的な誤りを(第一義的な真実と考えて)「われ思う、ゆえにわれ在り」という有名な言葉で表現した。
これは「自分が絶対的な確実性をもって知り得ることがあるだろうか?」という問いにデカルトが出した答えだった。
彼は自分がつねに考えているという事実は疑いようがないと考え、思考と存在を同一視した。
つまりアイデンティティ――私は在る――を思考と同一化したのである。
彼は究極の真実を発見する代わりにエゴの根源を発見したのだが、自分ではそれに気づいていなかった。
別の著名な哲学者が先の言葉にはデカルトが――同時に他の誰もが――見すごしていた部分があると気づくまでに、それから三百年近くを要した。
その哲学者はジャン―ポール・サルトルである。
彼はデカルトの「われ思う、ゆえにわれ在り」という言葉を吟味しているうちに、ふいに、彼自身の言葉によれば「『われ在り』と言っている意識は、考えている意識とは別だ」ということに気づいた。
これはいったいどういう意味か?
自分が考えていることに気づいたとき、気づいている意識はその思考の一部ではない。
別の次元の意識だ。
その別の次元の意識が「われ在り」と言う。
あなたのなかに思考しかなければ、思考しているなんてことはわからないだろう。
自分が夢を見ているのに気づかない夢中歩行者のようなものだ。
夢を見ている人が夢の中のすべてのイメージに自分を同一化するように、すべての思考に自分を同一化する。
多くの人々はいまもそんな夢中歩行者のように生き、古い機能不全の心の癖に囚われ、同じ悪夢のような現実をいつまでも再創造し続けている。
しかし自分が夢を見ていると気づけば、夢のなかで目覚める。
別の次元の意識が入り込む。
サルトルの洞察は深かったが、しかし彼は依然として自分を思考と同一化していたために、自分の発見の真の意味に、つまり新しい次元の意識が生まれたことに気づかなかった。
すべての理解にまさる安らぎ
人生のどこかで悲劇的な喪失に出合い、その結果として新しい次元の意識を経験した人は多い。
持ち物のすべてを失った人もいれば、子どもや配偶者を、社会的地位を、名声を、肉体的能力を失った人もいる。
場合によっては災害や戦争によってあらゆるものを同時に失い、「何も」残されていないことに気づいた人もいる。
それは「限界的な状況」と呼んでもいいだろう。
何に自分を同一化していたにせよ、何が自分自身という意識を与えていたにせよ、それが奪い去られた。
そこでなぜかわからないが、当初感じた苦悶や激しい恐怖に代わって、ふいに「いまに在る」という聖なる意識、深い安らぎと静謐と、恐怖からの完壁な自由が訪れる。
この現象は「人のすべての考えにまさる神の平安」という言葉を残した聖パウロにはなじみのものだったに違いない。
確かにこの安らぎは筋が通らず、人は自分に問いかける。
こんなことになったのに、どうしてこのような安らぎを感じられるのだろう、と。
エゴとは何でどのように作用するかがわかれば、答えは簡単だ。
あなたが自分を同一化していた形、自己意識を与えてくれた形が崩壊したり奪い去られたりすると、エゴも崩壊する。
エゴとは形との同一化だからだ。
もはや同一化する対象が何もなくなったとき、あなたはどうなるか?
まわりの形が死に絶えた、あるいは死にかけたとき、あなたの「大いなる存在」の感覚「私は在る(I am)」という意識は形の束縛から解放される。
物質に囚われていたスピリットが自由になる。
あなたは形のないあまねく存在、あらゆる形や同一化に先立つ「大いなる存在」という真のアイデンティティの核心に気づく。
自分を何らかの対象に同一化する意識ではなく、意識そのものとしての自分というアイデンティティに気づく。
これが神の平安である。
あなたという存在の究極の真実とは、私はこれであるとかあれであるとかではなくて、「私は在る」なのだ。
大きな喪失を経験した人のすべてがこの気づきを経験して、形との同一化から切り離されるわけではない。
一部の人はすぐに、状況や他人や不当な運命や神の行為の被害者という強力な精神的イメージや思考を創り出す。
この思考の形とそれが生み出す怒りや恨み、自己憐憫などの感情に自分を強く同一化するから、これが喪失によって崩壊した他のすべての同一化にたちまちとって代わる。
言い換えれば、エゴはすぐに新しい形を見出す。
この新しい形がひどく不幸なものだということは、エゴにとっては大した問題ではない。
良くも悪くも同一化できればいいのだ。
それどころか、この新しいエゴは前よりももっと凝縮されて強固で難攻不落である。
悲劇的な喪失にぶつかったとき、人は抵抗するか屈するかしかない。
深い恨みを抱いて苦々しい人生を送る人もあれば、優しく賢く愛情探くなる人もいる。
屈するとは、あるがままを受け入れることだ。
人生に向かって自分を開くのである。
抵抗すると心が縮こまって、エゴの殻が固くなる。
あなたは閉ざされる。
抵抗しているときに(否定的な状態のときに、と言ってもいい)どんな行動を取っても、さらに外部の抵抗にあう。
宇宙はあなたの味方にはならない。
人生は助けてはくれない。
シャッターが閉まっていたら、日光は入ってこられない。
抵抗せずにあるがままを受け入れると、意識の新しい次元が開ける。
そのとき行動が可能か必要であれば、あなたの行動は全体と調和したものとなり、創造的な知性と開かれた心、つまり条件づけられていない意識によって支えられるだろう。
状況や人々が有利に、協力的に展開する。
不思議な偶然が起こる。
どんな行動も不可能ならば、あなたは抵抗の放棄とともに訪れる平安と静謐のうちに安らぐだろう。
それは神のもとでの安らぎである。